「ハイバウンス=やさしい」は本当か?/25秋ウェッジ研究 #1
“ボーケイ独り勝ち”を阻止すべく、この秋各社がウェッジ新製品を続々と送り出してきた。ウェッジを選ぶ際、“ソール性能”(形状、バウンス)がモノをいうのはなんとなく分かっているが、各社共にグラインドやバウンス角のバリエーションが多く、どんなソールを選べばいいか分からない…。そんな人のために、今どきウェッジの「ソール」を研究した。(第1回/全6回)
バウンスが大きいウェッジが台頭している
ウェッジは、さまざまなライで打つクラブであり、局面によっては小技を使うこともある。そのため、ソール形状やバウンスが打ち方に合っていなければ、イレギュラーな状況に対応できないことは皆さんも経験的に知っているだろう。
クラブデザイナーであり、カスタムメーカー「ジューシー」を主宰する松吉宗之氏は、今どきのウェッジ市場をこう分析する。「日本の一般的な市場の傾向とウェッジ全般の傾向、そのどちらも牽引しているブランドは『ボーケイ』(タイトリスト)だと思います。簡潔に言うと、ボーケイ発でバウンスが強いウェッジが増えてきました」(松吉氏、以下同)
バウンスが大きいウェッジが増えた背景として、PGAツアーでウェッジの使い方・打ち方が変わった事実がある。
「昔のプロはフェースを開いてロブショットを打つなど、グリーン周りでいろいろなワザを駆使するイメージがあったと思います。そうした技巧派にはローバウンスが適していた。ところが今は、割とシンプルなウェッジ使いで、特にPGAツアーでは“当てたらおしまい”のような打ち方をする若手選手が増えている。というのも、PGAツアーは年々コースセッティングが厳しくなっていて、グリーンが強烈に速く、かつラフが長かったり強かったりする。そういうコースでしっかりと結果(スコア)を出すために、フェースを開くのではなく、バウンスを使って“バーン”と打ち込んでそのまま、みたいな打ち方が増えています」と松吉氏は分析する。
ボールを点ではなくゾーンでとらえていく。それを実現しやすいのが「ハイバウンス」と言うのだ。
かつてはプロや上級者は58度1本で多彩な球を繰り出していたが、今はそうではなくなってきたという。まさに、ウェッジは“多ロフト時代”を迎えている。
「60度台を入れて『高い球を打つならロフトが寝ているウェッジを使う』という流れになっています。従来のようにフェースを開いてカット打ちをすると、スピン軸が傾くため球が落ちてから横に転がってしまいます。しかし、もともとロフトが寝ているヘッドをストレートに打つほうが真っすぐなスピンがかかって寄る確率が高まるのではないか、ということ。1本でいろんな球を打ち分けるのではなく、多くのロフトを使い分ける方が合理的だと認識しているのでしょう」
ハイバウンスはボクたちにも効果的なのか?
一方で、バウンスが大きいウェッジが日本のアマチュアにもハマるかと言えば、そうとは限らない。
「どうしても『ハイバウンス=やさしい』というイメージが一般論として根づいてしまって、それが大前提にあるので、欧米で起こったウェッジのハイバウンス化が日本のアマチュアにとってもやさしい、という流れになっています。果たしてそれは真実なのか…注意しなければなりません」
では「ハイバウンスがやさしい」と言い切れないのはナゼなのか?
「前述のようにPGAツアーの強烈に速いグリーンでは、強めのラフからでも高い球を打って手前のピンに止めなければいけない。こういう状況ではロフトが大きくてバウンスが強いウェッジを“バン”って当てていくような打ち方をしなければいけません。ただし、そういうシチュエーションが、普通のアマチュアが楽しむ一般営業のコースにあるのか?そういう道具がホントに必要なのか?ということです」
むむむ??確かに…。
バウンス効果が強いワイドソールのウェッジは、以下の状況でこそ生きると松吉氏は補足してくれた。
「フカフカのバンカーとか深めのラフ、ボールが芝に沈み込んでいてさらに沈む可能性があるライからボールを運び出すとき。そういうところではシャープなソールだと刺さってしまいますが、幅広ソールやバウンスが大きければ潜り込んでいかないし、接地してから方向転換をしてヘッドを前に進めてボールを押し出してくれます。ところが、そういうウェッジで花道などの良いライから打つと、ソールの効果が強すぎてミスになることが多いです」
つまり、「シャープでバウンス効果が弱いウェッジ=難しい」ことの裏返しとして「ハイバウンス=やさしい」という認識が広まったと松吉氏は考える。
バウンスの助けを借りて打てていますか?
各モデルのウェッジには「バウンス角」というスペックが表記されている。ところが、数値は同じでもソールの幅や形状によって違いがあるし、バウンスの頂点がソールのどこにあるかによって効き具合は変わる。そもそも測り方の基準からして異なることもあって「ハイバウンス=やさしい」と、ひとくくりにはできないのだ。
「バウンスが大きいウェッジを使ったばかりに、インパクトする前にソールが当たることを“ダフった”と勘違い…。すると、ソールが地面に当たらないように、ボールをどんどん右に置き、ロフトを立てて上から入れて、フェース面をボールに当てようとします。ダフりたくないからバウンスが大きいウェッジを選んだはずなのに、こういう打ち方しかできなくなってしまい、ミス(ダフり・トップ)を生む。実はそういう人が大勢いらっしゃいます」と松吉氏は警鐘を鳴らす。
「インパクトの前にソールが地面に当たることは決して悪いことじゃありません。本来はそうやってバウンスの助けを借りていいショットを打つことが、ウェッジの目指している性能なんです。『ハイバウンス=やさしい』と盲目的に選んでしまった弊害が多くの人に現れているのではないでしょうか」
それでは次回、ボクらはどういうウェッジを選べば良いかを、松吉氏に具体的に解説してもらう。
文:新井田聡
取材・編集:中島俊介
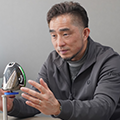
松吉宗之(まつよし むねゆき) プロフィール
ジューシー株式会社の代表取締役。ゴルフクラブメーカーにて、クラブの設計開発に20年以上携わる。2018年にジューシー株式会社を設立。自社製品だけでなく、OEMでの設計も行う。3D CADを用いたデジタル設計をいち早く導入し、数値に裏付けられた革新的な性能のクラブを多数開発。その傍ら、膨大な数のクラブヘッドを自身で測定し、ゴルフクラブの性能や製法の進化を独自に研究し続けている。








































