ソールのカタチ 「平ら」と「丸め」やさしいのはどっち?/25秋ウェッジ研究 #2
昨今のウェッジは、タイトリストの「ボーケイウェッジ」を筆頭に、ロフト角やバウンス角などスペックが充実している上、ソール形状のバリエーションも多い。それらの選択肢の中から自分にピッタリのソールを見つけるのはなかなか難しいところ。だが、我々アマチュアでも、簡単に見極めるポイントがあるという。(第2回/全6回)
「どの状況でどんな球を打ちたいか」で形状は決まる
「ボーケイウェッジ」を筆頭に、今どきのウェッジはソールグラインドのバリエーションが増えている。その点について、カスタムメーカーの「ジューシー」を主宰する松吉宗之氏はこう述べる。
「プロゴルファーとの接点が多いメーカーほど、いろいろなソール形状を市販しています。それは“ミスを助けるため”ではなく“どういう状況でどんな球を打ちたいか”が選手によって異なり、それに対応している結果。ある形状が良いという選手が増えれば、それが市販モデルにラインアップされるのでしょう」(松吉氏、以下同)
その松吉氏自身も、クラブ設計家として“ミスをどうカバーするか”ではなく“良いショットを打ちやすくする”ことに重きを置いてウェッジを開発しているという。
「たとえば悪条件のライやバンカーで、どういう性能だったらイメージ通りの球が打てるのかを考えて設計しています。一般のアマチュアがウェッジを選ぶとき『ミスをカバーしてくれるモノ』とか『バンカーからやさしく出るモノ』となりがちではないでしょうか。ですが、ミスしたときに“結果オーライ”になるウェッジと、良いショットが打てるウェッジはイコールではありません。そこを混同している人が意外に多いと思います」
ポイントは、ソールが平らか丸いか
松吉氏は、アマチュアが自分に適したウェッジを見極めるコツをアドバイスしてくれた。カンタンに言うと「ソールのトウ-ヒール方向が平らか、丸いか」。ではソールが平らなタイプは、どういう特徴があるのだろうか。
「平らなソールは跳ね方などの“個性”が強く、ミスに対してシビアです。というのも、平たい面が正面から当たるのと斜めに当たるのでは、働きがゼンゼン異なるから。平らな面がしっかり当たるように打たないと効果を発揮しません。必然的に、プロや上級者などいつも同じように打てる人やそう打とうとする人は、平らなソールを多く選びます。特にプロは、平らなソールの後ろ側を削って当たり具合を調整していきます。ソールの平らな面が当たれば、抜けが良く感じたりバウンスの効果がハッキリ表れたりするはずです」
平らなソールのウェッジをアマチュアが手に入れたときには、チェックすべきことがあるという。
「まずはライ角をきちんと合わせることが肝心です。ライ角が合っておらずいつもヒール側やトウ側から当たっているなら、平らなソールの効果が生かせません」
丸いソール、実はアマチュア向けだった!
ソールが丸いほうがテクニシャン向けだと思いがちだが、そうとは限らない。
「丸いソールはフェースを開閉するなどしても当たるところが同じというか、ソールの効果が同じように発揮されます。いろいろな打ち方をしたい人は丸いソールを選びますが、逆に言えば、スイングが安定しておらず入り方がバラついてしまう人を助けてくれる。テクニシャンと安定していない人の両方に効果があるのです」
ウェッジはロフトを調角することもあるが、それに伴ってバウンス角も増減する。原理として、ロフトを立てるとバウンスが減り、寝かせるとバウンスは増える。そのようにロフトを動かしたときの影響の度合いも、ソールが平らか丸いかで異なる。
「ソールが丸いとロフトを調角してバウンス角が変わっても、ソールの当たり方はそれほど変わらず、影響は少ないです。逆に、平らなソールはロフトをいじってバウンスが1度変わるとソールの当たり具合がそのまま変わるので要注意。特にロフトを立てる方向に調角するとシビアになりすぎるかもしれません」
フェースを開くなら、トウ側のバウンスにも気をつけたい
前回述べたように、アプローチでフェースを開いて打つことは、海外では主流じゃないかもしれない。しかし、いま持っているウェッジのフェースを開き、高い球で止めなきゃいけないケースがプロにも僕らにも、ある。
フェースを開いて打つには、ヒール側が落とされたソールが良いのは間違いない。一方で、トウ側はどう関わるのだろうか?
「ソールのヒール側が落ちていると、フェースを開いたときに抵抗が少ないので芝に入りやすいですが、トウ側のバウンスが効いてきます。トウ側が当たってほしければ残すし、当たり過ぎがイヤなら削ります。ここは選手の好みですね」
そもそも、フェースを開いて打つとどんな効果があるのだろうか?
「効果は3つあります。ひとつは、より高い球が打てること。フェースを開くとロフトが増えるので、高い球を打ちたければ開いてロフトを寝かせればいいのです。もうひとつは、ラフや砂の抵抗が減らせること。フェースを開き、打つ方向に対しての“面積”を小さくすれば、抵抗が抑えられます。
最後はウェッジ選びのポイントでもあるのですが、ソールが当たる位置をシャフトより後方にすることで、ミスを抑えられます。シャフトの真下でソールが接地すると、上から圧がかかるので潜ることもある。しかしシャフトより後方で着地すると、潜らず前に滑ってミスになりづらいです。シャフトより後方で着地しやすいカタチにはワイドソールや大きなバウンス角、グースネックなどがありますが、フェースを開くことでもその効果を得られます」
次回は、今どきウェッジをツアープロがコースで試打したので、そのインプレッションを紹介する。
文:新井田聡
取材・編集:中島俊介
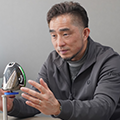
松吉宗之(まつよし むねゆき) プロフィール
ジューシー株式会社の代表取締役。ゴルフクラブメーカーにて、クラブの設計開発に20年以上携わる。2018年にジューシー株式会社を設立。自社製品だけでなく、OEMでの設計も行う。3D CADを用いたデジタル設計をいち早く導入し、数値に裏付けられた革新的な性能のクラブを多数開発。その傍ら、膨大な数のクラブヘッドを自身で測定し、ゴルフクラブの性能や製法の進化を独自に研究し続けている。











































